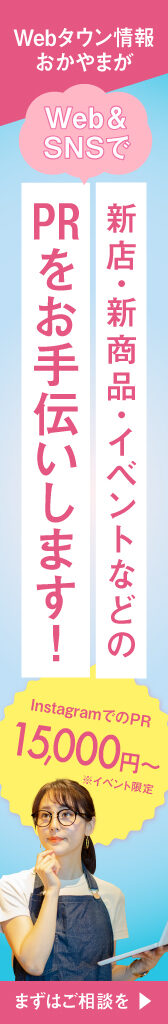最終回。『ハレノワ』の歩みを振り返り、
岡山の歴史や文化、芸術を未来へ。
『岡山芸術創造劇場 ハレノワ』が開館することをきっかけに、改めて地域の歴史や街の人を紹介しようと、2021年3月からスタートしたこのコーナー、ついに最終回を迎えました! vol.1でわかるように、連載開始当初は、まだ『ハレノワ』は建設中。開館する3年以上前から設立されていた準備室も、岡山市民会館の中にあり、取材はそこから始まったのでした。

ということで、最終回は『岡山芸術創造劇場 ハレノワ』事業グループの加賀田浩二さん、岡本愛美さんとともに、これまでの歩みを振り返っていきます。※vol.1~42&特別編は、巻末の「バックナンバーはこちらから」より閲覧できます

―――加賀田さんに最初にお会いしたのは、開館前。劇場開館準備室が定期的に開いていた、劇場と街の関わりあいなどをテーマに地域の人々と意見交換する、プレ事業「vol.13」を取材した時でした。

加賀田/私は準備室立ち上げ当初から担当させていただきました。ゼロからのスタートでしたので、まずは新しい劇場を周知してもらうことから始めました。初めて表町商店街にアプローチしたのが、岡山市表町商店街連盟代表理事で『長谷川楽器店』社長の長谷川誠さん(※vol.5参照)に、ご挨拶してお話を伺った時。地域の歴史など3時間くらい商店街のことをていねいに話してくださって。私は、以前、商店街で街のプロジェクトを担当したこともありましたが、地域のことをここまで熱く語る人は、そんなにいないと思いました。
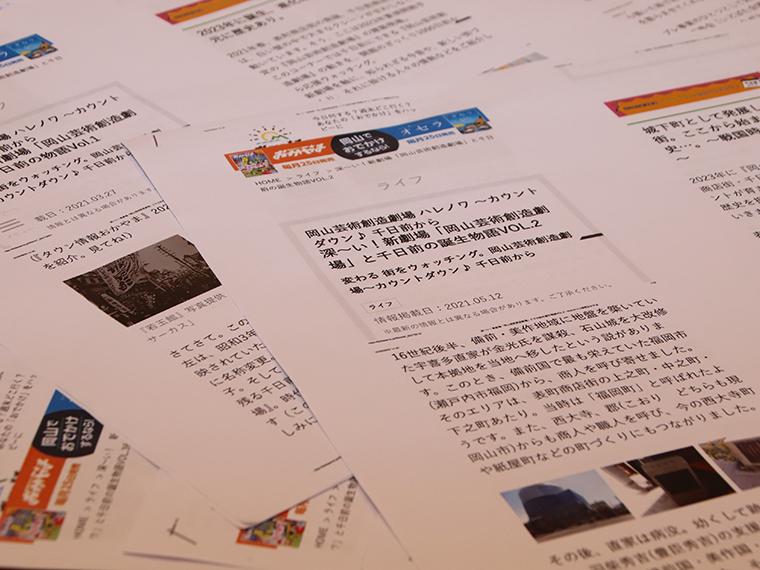
また、プレ事業でいろんなワークショップを開きましたが、コロナ禍でも定員オーバーになることが多くて、岡山は自発的に何かしたい人が多いのかなと、可能性を感じました。岡山のように開館の2年以上前からプレ事業をたくさんする施設は珍しいんです。
―――加賀田さんが以前、「コロナ禍に、国内有数の規模で誕生する『ハレノワ』は、全国的に注目されている」と言われていました(vol.13参照)。お二人にとって、その時期のプレ事業で、強く印象に残ったことはありますか?

岡本/よく覚えているのは、『ハレノワ』開館日に披露する「100人ダンス」の準備のために2022年に開いた、小学生から参加可能のワークショップ(vol.15)です。振付家・ダンサー・俳優の北尾亘さんに講師を務めていただき、盆踊りのようなオリジナルダンスを踊りました。皆さんの踊りが終わると同時に、繰り返し流れていた音楽もピタッと終わって! 小さな奇跡みたいな瞬間。参加者皆で「わーっ、すごい!」って (笑)。年代も生まれた場所も違う、その場で初めて出会った人たちなのに、絆と一体感が生まれたと感じました。
▲2023年9月の『ハレノワ』開館日に披露した「100人ダンス」。表町商店街北端から振付・演出の北村成美さん率いるダンスパレードが出発。南端の『ハレノワ』に到着後、北尾さんの音頭による「born dance」でお祝い
加賀田/そうですね。私にとっても「100人ダンス」は特別なイベントで、純粋に楽しかったなぁって(笑)。まだ劇場ができてなかったから、地域のコミュニティセンターのちっちゃい部屋を借りてワークショップが始まって…。みんなで周辺の街を歩いたり、岡山の魅力を考えたり。盆踊りに着想を得て具現化していく過程を市民も職員も一緒に楽しめたことは、理想的なクリエイティブな場になったと思うんです。
―――「100人ダンス」の時、表町商店街をハレノワダンサーズがパレードして『ハレノワ』のエントランスに到着して。観客も巻き込んで、「born dance」を踊りました。1950年代のお祭りの写真がありましたけど(vol.22参照)、そんな賑わいが再来した感じでした。
加賀田/まさに、「いどばた会議」で見たその頃の祭りの、南極船を模した山車の写真にインスパイアを受けて、「ソウゾウのフネ」の山車を作ってダンスパレードしようと企画したんです(vol.24参照)。開館日に多くの人の想いが結集して、重ねてきたワークショップの集大成を地元商店街で披露できたことがとても感動的でした。
―――『ハレノワ』が開館してから、特に印象的な舞台は?
岡本/やはり、こけら落としのオペラ「メデア」でしょうか(vol.23参照)。日本初演のギリシャ悲劇で、岡山フィルハーモニック管弦楽の生演奏でお送りしました。
加賀田/チケットも早々に完売して反響がすごかったです。オペラは人間の体そのものが楽器になるといいます。舞台のクオリティも別次元でした。『メデア』で初めてオペラを観た人も多かったと思います。

岡本/職員は会場準備やお客様の対応に追われていましたね(笑)。開館後、半年間で本当に様々な公演を行ったので、23年度は忘れられない年になりました。
―――『ハレノワ』を利用された方からの印象的な声はありますか?
加賀田/お客様から、「中劇場は鑑賞しやすい」とよく言われますね。客席と舞台が近くて…。演者さんからも「お客さんの顔がよく見えて、空気感まで伝わってきて演じやすい」「岡山の人はストレートに反応してくれるから嬉しい」などと言われます。名だたるカンパニーさんが「また岡山でやりたい」と言ってくださっていると、業界では噂になっているようです(笑)。だけど、開館から2年かけての評価。舞台に客席が近い分、床の傾斜が強めで、手すりを付けるなど、お客様の声もお聞きして工夫してきました。
岡本/「県外に行かないと観ることができないような作品を岡山で観ることができた」という声もたくさん頂いています。
加賀田/2025年度の目玉は、劇作家フェスティバル「げきじゃ!」が岡山に来ること (vol.38参照)。全国から劇作家が集い、演劇の楽しさを体験できる4日間です(2025年10月31日~11月3日)。『ハレノワ』のラインナップは、現代社会を反映したテーマ性のあるものも多い。そこが公共施設ならではだと思います。
―――同じ舞台でも他の劇場より入場料を調整したり、学生料金があったりと、利用しやすい配慮をされていますね。また『ハレノワ』の「つくる」事業もどんどん増えている気がします。

加賀田/『ハレノワ』の大きな特徴は、作品を創造することです。今年度は『ハレノワ』発の作品として、岡山在住のダンサー・平井優子さんの演出・振付で、ダンスと現代サーカスが融合した「Disco on the planet」を11月に上演します。また、岡山のNPO法人「アートファーム」と共同で、地元の老舗が軒を連ねる京橋町の戦前から現代までを舞台化した「わが町」プロデュース公演『京橋あけぼの通り』をつくっていて、2026年2月(7日、8日)に上演予定です(vol.30参照)。
岡本/もうひとつの「つくる」事業が、昨年から3年計画で動いている「ミュージカルアカデミー」です。オーディションで選ばれた市民の方が出演し、オリジナルミュージカル「拝啓 ナイチンゲール様」(vol.40参照)を、2025年8月にプレ公演として上演しました。来年、全編を上演するんですが、タイムリーなことに、原作が来年のNHK連続テレビ小説の題材にもなるんです。
加賀田/全国的にみてもこれだけ自由に、実験的に創作ができる劇場は少ないらしくて。今後もそういう劇場であり続けないと。時代や人をつないでいった上で、新しいものを生み出すことが肝だと思ってます。市民と舞台芸術を結ぶワークショップも多彩に行っています。高齢者や高校生とともに舞台をつくる試みも毎年恒例で(vol.26、vol.32)。国内外で活躍している講師を招き、参加者それぞれの考えを引き出したり、今までの経験からくるアドバイスも魅力です。

岡本/いかに市民の方々に使って頂ける劇場になるか、ということもすごく大事だと思っています。身近な存在になれるよう、職員一同心がけています。いろんな市民の声を聞いて改善していきたいし、いい作品を皆さんに観ていただきたい。憩いの場でありつつ、非日常になれる場所でありたいです。

当コーナーの立ち上げには、『月刊タウン情報おかやま』の創刊者であり、株式会社ビザビの故・前坂匡紀会長の言葉が背景にありました。「表町に『ハレノワ』が開館するのは本当にすばらしいこと。でも、劇場だけが単体で頑張るのではなく、地域みんなで一緒に盛り上げることが大切。そのためにも、地域の歴史や街の人の声を共有し、愛着が生まれるような情報を発信する、タウン誌ならではのコーナーにしてほしい」。
この言葉を受けて、4年半にわたる連載では、番外編2回を含む全44回の記事を掲載してきました。劇場を核としながらも、タウン誌だからこそ伝えられる「地域を主役にした物語」を発信してきました。これからも、『ハレノワ』から「晴れの国おかやま」の芸術と文化が生まれ、地域に新たな刺激を与え、人々に笑顔の花が咲き、やがて大きな輪となってつながっていきますように。
<消費税率の変更にともなう表記価格についてのご注意>
※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください