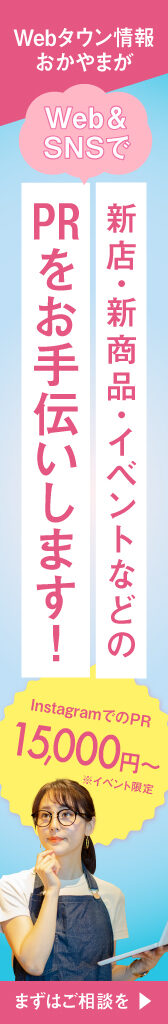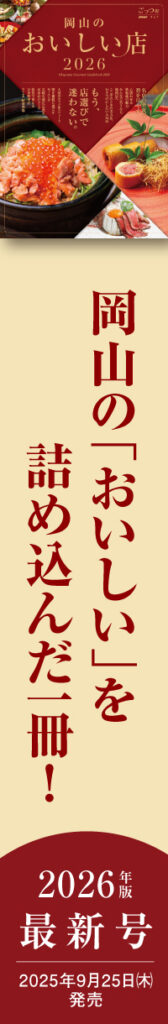映画『国宝』で高まる歌舞伎への注目。奈義町に息づく農村歌舞伎「横仙歌舞伎」
映画『国宝』の公開を機に、再び注目を集めている歌舞伎。
作中ではプロの歌舞伎役者の世界描かれていますが、岡山をはじめ日本各地には地域の人々が演者や義太夫を務め、独自に継承してきた「農村歌舞伎」が今も息づいています。
奈義町で受け継がれている「横仙(よこぜん)歌舞伎」もそのひとつ。春と秋の年2回公演が行われ、地域の文化として大切に守られてきました。
今回は、11月22日(土)・23日(日)に迫る秋公演に向け、11月上旬に行われた稽古の様子を特別に見学! こちらの記事では貴重な稽古の様子をお届けします。
農村歌舞伎 「中島東松神座」の稽古へ
この日、稽古を行っていたのは奈義町・中島東地区を拠点に活動する「中島東松神座」。
歌舞伎は「男性が演じるもの」というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、近年は女性の参加もあるとか。さらに2025年度からはフランス人のメンバーも加わり、地域に開かれた新しい形の歌舞伎として進化しています。
また、奈義小学校では「総合的学習の時間」で歌舞伎の授業が行われており、次代を担う子どもたちが着実に育っているのも印象的。
三味線に合わせて動きとせりふを確認。受け継がれる技と教え

稽古場では、浴衣姿の役者たちが三味線の音に合わせ、動きやせりふを確認。
指導に当たるのは、50年以上にわたり「横仙歌舞伎」に携わってきた重鎮。せりふまわしの節、身体の使い方など、細やかな指導が次々と飛びます。
真剣ながらもどこか温かい空気の中で稽古が進む様子を見ていると、秋公演への期待が自然と高まります。
衣装もメイクも地元で。地域総出で作り上げる舞台

横仙歌舞伎で使用する着物やかつら、小道具の多くは奈義町で保有しているもの。本番当日は仲間同士で着付けを行い、化粧も担当。
奈義町では「中島東松神座」と「横仙歌舞伎保存会」が活動しており、秋公演ではこの2団体に加え、「横仙こども歌舞伎教室」や美作市の「粟井春日歌舞伎保存会」による演目も披露される予定です。
地元の人の声援を受けながら、今年はどのような演技が披露されるのか。
秋公演は入場無料。なかなか触れる機会の少ない歌舞伎の世界を、まずは岡山県内の歌舞伎鑑賞から体験してみては。
<消費税率の変更にともなう表記価格についてのご注意>
※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください